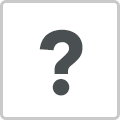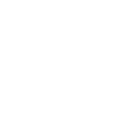私の日本語辞典「盆山から盆栽へ~言葉でたどる“盆栽”の歴史」(1-4)
番組表検索結果 | NHKクロニクル
テーマ

一か月
 ~
~

 ~
~

 ~
~

テーマ
2019年1月の放送予定
盆山から盆栽へ~言葉でたどる「盆栽」の歴史
講師:依田 徹(遠山記念館学芸部長)
盆栽は、古く「盆山(ぼんさん)」と呼ばれていたといいます。平安時代には「鉢植えの木」として親しまれていたようで、ほかにも「鉢の木」「作り松」など、「盆栽」を示す用語(言葉)は定着していませんでした。江戸時代の記録には「盆栽」という表記はでてきますが、そこに「ハチウエ」とカナがふってありました。
依田徹さんは、東京芸大大学院美術研究科を卒業、茶道史や日本近代美術史の研究を続ける中で、このほど盆栽の歴史を『盆栽の誕生』という著書にまとめました。平安時代から近世までの盆栽文化の発展過程について、時代ごとの呼称や表現をキーワードと共に詳しく述べています。
番組では、日本の伝統文化のひとつである『盆栽』の歴史を「言葉」をてがかりに、話してもらいます。
放送は4回シリーズ。
聞き手:NHK放送研修センター日本語センター 秋山和平アナウンサー
依田徹さんは、東京芸大大学院美術研究科を卒業、茶道史や日本近代美術史の研究を続ける中で、このほど盆栽の歴史を『盆栽の誕生』という著書にまとめました。平安時代から近世までの盆栽文化の発展過程について、時代ごとの呼称や表現をキーワードと共に詳しく述べています。
番組では、日本の伝統文化のひとつである『盆栽』の歴史を「言葉」をてがかりに、話してもらいます。
放送は4回シリーズ。
聞き手:NHK放送研修センター日本語センター 秋山和平アナウンサー
<内容>
1回 依田さんが「盆栽」の歴史について研究をはじめたきっかけと、平安時代以降の文献などに見える盆山(ぼんさん)、鉢の木などについて
2回 江戸時代に盛んになる盆栽について、またこの時代に特にはやった人工的な曲物作りについて
3回 江戸末期以降の「盆栽誕生」について
4回 明治以降の政財界や皇室と盆栽のかかわりについて
1回 依田さんが「盆栽」の歴史について研究をはじめたきっかけと、平安時代以降の文献などに見える盆山(ぼんさん)、鉢の木などについて
2回 江戸時代に盛んになる盆栽について、またこの時代に特にはやった人工的な曲物作りについて
3回 江戸末期以降の「盆栽誕生」について
4回 明治以降の政財界や皇室と盆栽のかかわりについて
出演者プロフィール

依田 徹(よだ・とおる)
1977年、山梨県生まれ。東京藝術大学大学院美術研究科学術学専攻、博士後期課程修了。美術博士。専門は、日本近代美術史、茶道史。
<主な著書>『近代の美術と茶の湯』『十三松堂茶会記』『盆栽の誕生』など多数。
<主な著書>『近代の美術と茶の湯』『十三松堂茶会記』『盆栽の誕生』など多数。


「盆山から盆栽へ~言葉でたどる“盆栽”の歴史」(4)
遠山記念館学芸部長…依田徹,【アナウンサー】秋山和平
明治に入ってから、盆栽は政財界の要人や皇室に広まります。明治天皇は病気の重臣を見舞うとき、盆栽を持っていったことが記録に残っています。また皇室に献上される盆栽も多く、明治時代に立てられた宮殿には盆栽が飾られていました。最後に、盆栽とは何か、改めて依田さんの考え、「盆栽とは木との対話である」が示されます。


「盆山から盆栽へ~言葉でたどる“盆栽”の歴史」(3)
遠山記念館学芸部長…依田徹,【アナウンサー】秋山和平
江戸時代末期になると、盆栽の流行はそれまでの人工的な作り物から、木の自然さを生かすものに変わっていきます。その原因は、当時の中国趣味にあったと見られています。「自然」ということばは、もともと仏教の「自然(じねん)」という考え方からきていますが、「ネイチャー」という外国語を翻訳するとき、「自然」をそれにあてました。明治以降の盆栽では、「自然」がキーワードとなります。


「盆山から盆栽へ~言葉でたどる“盆栽”の歴史」(2)
遠山記念館学芸部長…依田徹,【アナウンサー】秋山和平
「盆栽」が「誕生」したのは、江戸時代に入ってからです。徳川家代々の将軍に、諸国の大名が盆栽を献上することが増えました。三代将軍家光は盆栽を好んだことで知られますが大久保彦左衛門が家光をいさめるため盆栽を壊した話が残っています。江戸時代の盆栽は器に有田焼を用い当時完成した染付がついたものが好まれました。また人工的に作られた「つくり」が多く作られました。中心の幹をS字に曲げた松などが流行したようです。
| 2019年01月05日(土) 午後03:10~午後03:40 |
| 「盆山から盆栽へ~言葉でたどる“盆栽”の歴史」(1) |
| 盆栽とはなんなのでしょうか?鉢に植え育てながら、その形に手を加え、年月をかけて一つの景色を生み出していきます。「木と対話しながら」形づくっていくものです。盆栽という言葉自体が定着したのは明治時代に入ってからでした。それ以前は鉢の木(鉢木;はちのき)、盆山(ぼんさん)でした。今回は「盆栽」の歴史を、平安時代の文献などを見ながら中世までたどります。 |